OBIC7は、株式会社オービックが提供するERPシステムで、会計業務から人事業務まで企業活動の情報を一元管理できるソリューションです。クラウド型とオンプレミス型から選択でき、中小企業から大企業まで幅広い企業規模に対応しています。本記事では、OBIC7の基本機能や特徴、導入メリット、料金プラン、他システムとの比較、導入時の注意点まで詳しく解説します。
目次
OBIC7とは?株式会社オービックが提供するERPシステムの概要
OBIC7の基本的な定義とコンセプト
OBIC7は、株式会社オービックが開発・提供する統合型ERPシステムで、企業の基幹業務を一元管理できる包括的なソリューションです。OBIC7のコンセプトは、企業活動に必要な会計、人事、販売、生産などの業務システムを統合し、情報を一元管理することで業務効率化と経営の透明性向上を実現することです。
OBIC7は、企業規模に応じて柔軟にカスタマイズできる設計となっており、中小企業から大企業まで幅広い企業に対応しています。システムは、クラウド型とオンプレミス型の両方の導入形態を提供し、企業のニーズや既存システム環境に合わせて最適な導入方法を選択できる特徴があります。
株式会社オービックの企業概要と開発背景
株式会社オービックは、1968年に設立された日本を代表するシステムインテグレーターで、ERPシステム分野において長年にわたって豊富な実績を積み重ねてきました。同社は、日本企業特有の商慣習や法制度に精通しており、OBIC7の開発においても日本企業のニーズを深く理解した機能設計が行われています。
OBIC7の開発背景には、従来の個別システムでは対応できない企業の複雑な業務要求や、急速に変化する経営環境への対応力強化があります。株式会社オービックは、これらの課題を解決するため、最新のテクノロジーを活用しながら、使いやすさと機能性を両立したERPシステムとしてOBIC7を開発しました。
ERPシステムとしての位置づけと市場シェア
OBIC7は、日本のERPシステム市場において高い評価を受けており、特に中堅・中小企業向けのERPシステムとして確固たる地位を築いています。ERPシステムとしてのOBIC7は、企業資源計画の最適化を支援し、経営判断に必要な情報をリアルタイムで提供する機能を備えています。
市場における OBIC7の位置づけは、日本企業の業務特性を深く理解した国産ERPシステムとして、外資系ERPシステムとは差別化された価値を提供している点にあります。導入実績の豊富さと、継続的な機能改善により、多くの企業から信頼を獲得しています。
OBIC7が対象とする企業規模と業種
OBIC7は、従業員数50名程度の中小企業から、数千名規模の大企業まで幅広い企業規模に対応しています。特に、年商数億円から数百億円規模の中堅企業において、その柔軟性と機能性が高く評価されています。
対象業種については、製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業など、幅広い業界での導入実績があります。OBIC7は業界特有の業務要件にも対応できる豊富な機能を提供しており、各業界のベストプラクティスを反映したソリューションを提供しています。
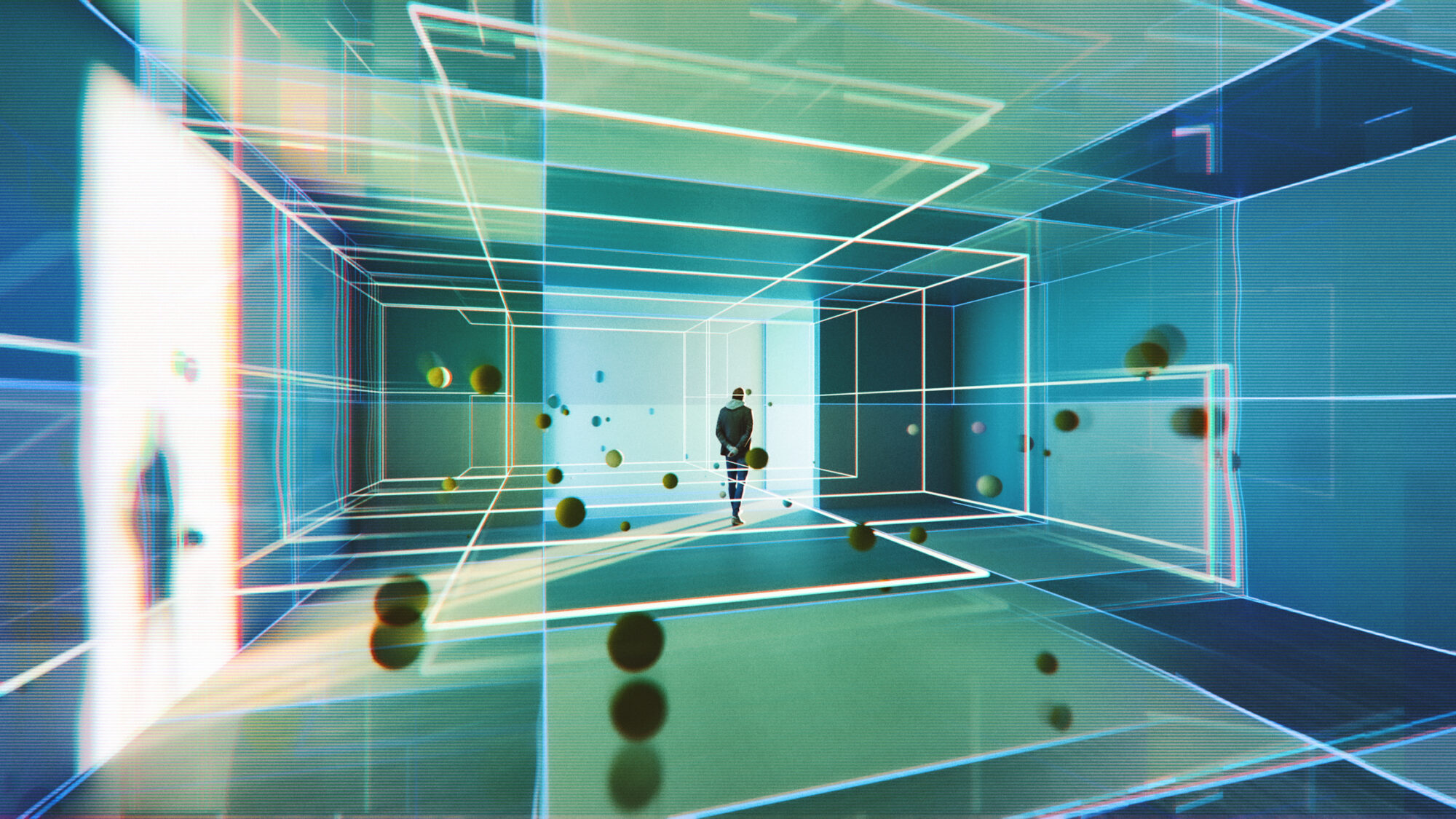
OBIC7の主要機能とシステム特徴
会計業務の包括的な管理機能
OBIC7の会計業務機能は、単体会計から連結会計まで対応し、包括利益対応や固定資産管理など、企業の会計業務を包括的にサポートします。自動仕訳機能により、定型的な仕訳処理を自動化し、経理担当者の業務負荷を大幅に軽減できます。
会計システムとしてのOBIC7は、リアルタイムでの財務状況把握を可能にし、月次決算の早期化や正確性向上に貢献します。また、税制改正や会計基準の変更にも迅速に対応し、常に最新の会計要件を満たすシステム運用が可能です。
人事業務・給与計算・就業管理システム
OBIC7の人事業務機能は、採用から退職まで従業員のライフサイクル全体を管理し、給与計算、勤怠管理、人事異動などの業務を統合的に処理できます。人事システムとしての機能は、複雑な給与体系や勤怠ルールにも柔軟に対応し、法改正にも迅速に対応する体制が整っています。
就業管理機能では、多様な勤務形態に対応し、テレワークやフレックスタイム制度にも対応しています。人事業務のデジタル化により、従業員情報の一元管理と、人事戦略の立案に必要なデータ分析機能も提供されています。
販売業務・生産業務・財務業務の統合管理
OBIC7は、販売管理から生産管理、在庫管理まで、企業の中核となる業務プロセスを統合的に管理できる機能を提供します。受注から出荷、請求まで一連の販売業務フローを自動化し、業務効率化を実現します。
生産業務においては、生産計画から製造実績管理まで対応し、製造業特有の複雑な業務要件にも対応しています。財務業務では、予算管理や資金繰り管理など、経営管理に必要な機能が充実しており、経営判断をサポートする豊富な分析機能も提供されています。
ワークフロー機能とデータ連携の仕組み
OBIC7のワークフロー機能は、承認業務の効率化と内部統制の強化を同時に実現します。経費精算、稟議書、各種申請書など、企業内のさまざまな承認プロセスを電子化し、承認状況の可視化と処理時間の短縮を図ります。
データ連携機能については、OBIC7内の各モジュール間でのデータ を連携させるだけでなく、外部システムとのAPI連携も可能です。既存システムとの連携により、段階的なシステム移行や、特定業務に特化したシステムとの併用も実現できます。
内部統制・セキュリティ機能の特徴
OBIC7は、企業の内部統制要件に対応した豊富な機能を提供しています。ロギング機能により、システム内での全ての操作履歴を記録し、監査対応や不正防止に活用できます。また、職務分離や承認権限の設定により、適切な内部統制環境の構築をサポートします。
セキュリティ面では、多層防御の考え方に基づいた堅牢なセキュリティ機能を提供し、企業の重要な情報資産を保護します。定期的なセキュリティアップデートにより、最新の脅威に対する対策も継続的に強化されています。

OBIC7のクラウド型とオンプレミス型の違い
クラウド型OBIC7の特徴とメリット
クラウド型OBIC7は、インターネット経由でシステムを利用するSaaS形式で提供され、初期投資を抑えた導入が可能です。クラウド型の最大のメリットは、サーバーやネットワーク機器の購入・保守が不要で、システムの運用管理をオービックに委託できる点です。
また、クラウド型では自動的にシステムアップデートが適用されるため、常に最新の機能と法改正対応を利用できます。災害時のBCP対策としても有効で、データのバックアップや復旧もクラウド基盤により自動化されています。リモートワークにも対応しやすく、場所を選ばずにシステムを利用できる特徴があります。
オンプレミス型OBIC7の特徴とメリット
オンプレミス型OBIC7は、企業の自社環境にシステムを構築する形態で、システムの完全な管理権限を企業側が持つことができます。既存システムとの詳細な連携や、企業固有の要件に対する高度なカスタマイズが可能な点が最大のメリットです。
オンプレミス型では、企業のセキュリティポリシーや規制要件に応じて、詳細なセキュリティ設定や運用ルールを設定できます。また、大量のデータ処理や複雑な業務処理においても、専用環境により安定したパフォーマンスを確保できる特徴があります。
導入形態別の比較表と選び方のポイント
クラウド型とオンプレミス型の選択においては、企業の規模、業務要件、IT リソース、セキュリティ要件などを総合的に検討する必要があります。
- 初期コストを抑えたい場合:クラウド型が適している
- 高度なカスタマイズが必要な場合:オンプレミス型が適している
- IT管理リソースが限られている場合:クラウド型が適している
- 既存システムとの密な連携が必要な場合:オンプレミス型が適している
- 迅速な導入を希望する場合:クラウド型が適している
企業のビジネス戦略と IT戦略を整合させながら、長期的な視点で最適な導入形態を選択することが重要です。
データ を一元管理する際の注意点
OBIC7によるデータ の一元管理では、データ品質の確保と一貫性の維持が重要な注意点となります。複数のシステムから移行するデータの整合性チェックや、重複データの排除など、データクレンジング作業を適切に実施する必要があります。
また、データ を一元管理することで、システム障害時の影響範囲が広がる可能性があるため、適切なバックアップ戦略と災害復旧計画の策定が不可欠です。データアクセス権限の設定についても、職務に応じた適切な権限管理を行い、情報セキュリティを確保する必要があります。

OBIC7導入のメリットと企業活動への効果
情報を一元管理することによる業務効率化
OBIC7のERPシステムは、企業の各部門で散在していた情報を一元管理することで、大幅な業務効率化を実現します。従来の個別システムでは、会計業務、人事業務、販売業務がそれぞれ独立したシステムで管理されており、データの重複入力や転記ミスが頻発していました。
OBIC7を導入することで、企業活動に必要な全ての情報が統合され、リアルタイムでのデータ共有が可能となります。これにより、月次決算業務の迅速化や、経営判断に必要な情報の即座な取得が実現されています。
さらに、システムの自動仕訳機能により、手作業による入力作業が大幅に削減され、経理担当者の生産性向上に貢献しています。ワークフロー機能により承認プロセスも効率化され、企業全体の業務スピードが向上します。
企業規模に応じた柔軟なカスタマイズ性
OBIC7は、中小企業から大企業まで、企業規模に応じた柔軟なカスタマイズが可能なERPシステムです。株式会社オービックが長年培ってきたノウハウにより、業界特有の業務要件にも対応しています。
製造業では生産管理機能、建設業では工事進行基準に対応した会計機能、サービス業では顧客管理機能など、業界ごとの特殊な業務プロセスに対応したソリューションが提供されています。
また、企業の成長に応じてシステムの機能を段階的に拡張できるため、初期導入時は基本的な会計システムから始めて、必要に応じてCRMや生産管理などの機能を追加導入することが可能です。
法改正・制度改正への対応力と生産性向上
OBIC7の大きなメリットの一つは、法改正や制度改正への迅速な対応力です。電子帳簿保存法、インボイス制度、包括利益対応など、頻繁に変更される法制度に対して、株式会社オービックが継続的にシステムアップデートを提供しています。
これにより、企業は法改正のたびにシステム改修コストを心配する必要がなく、本業に集中できる環境が整います。特に会計業務においては、法定帳票の自動作成機能により、決算業務の大幅な効率化が実現されています。
内部統制機能も充実しており、上場企業に求められるJ-SOX法への対応も万全です。監査証跡機能により、データの変更履歴が自動で記録され、監査対応の負荷軽減にも貢献しています。
BCP対策と高いスケーラビリティの実現
OBIC7のクラウド型では、災害時でも業務継続が可能なBCP(事業継続計画)対策が標準で組み込まれています。データセンターの冗長化により、システムの可用性が高く保たれており、企業活動の継続性を確保します。
スケーラビリティの面では、企業の成長に合わせてユーザー数やデータ容量を柔軟に調整可能です。拠点数の増加や海外展開時にも、迅速にシステム対応が行えるため、企業の事業拡大を強力にサポートします。
オンプレミス型においても、サーバー増強による性能向上が容易であり、企業の成長段階に応じた最適なシステム環境を維持できます。
豊富な導入実績による安心感とサポート体制
OBIC7は豊富な導入実績を誇り、累計で数千社以上の企業に導入されています。この実績により、業界別のベストプラクティスが蓄積されており、導入時の参考事例が豊富に存在します。
株式会社オービックのサポート体制も充実しており、導入前のコンサルティングから導入後の運用支援まで、一貫したサービスが提供されています。24時間365日のサポート体制により、システムトラブル時の迅速な対応が保証されています。

OBIC7の料金プランと導入コスト
基本的な料金体系と価格設定の考え方
OBIC7の料金体系は、企業規模と利用する機能に応じた段階的な価格設定となっています。クラウド型とオンプレミス型で料金構造が異なり、それぞれの導入形態のメリットを活かした価格設定が行われています。
クラウド型では月額利用料金制を採用し、初期導入コストを抑えながら利用開始できる仕組みとなっています。一方、オンプレミス型では、ライセンス一括購入により長期的なコストメリットを享受できます。
料金プランには基本的な会計機能から、人事業務、販売管理、生産管理まで、段階的に機能を追加できるオプション制が採用されており、企業の成長に応じた投資が可能です。
企業規模別の導入コスト目安
中小企業(従業員50名以下)の場合、基本的な会計システムの導入であれば、初期費用200万円程度、月額利用料10万円程度からスタート可能です。人事業務や販売管理機能を追加する場合、追加で月額5-10万円程度の費用が発生します。
中堅企業(従業員100-500名)では、より包括的なERPシステムとしての導入となるため、初期費用500-1,000万円、月額利用料30-80万円程度が一般的な相場となります。
大企業(従業員500名以上)での導入では、カスタマイズ要件が高くなるため、初期費用1,000万円以上、年間運用費用も数百万円から数千万円規模となることが多く見られます。
初期費用・月額費用・保守費用の詳細
OBIC7の導入に必要な費用は以下の要素で構成されています。
- ライセンス費用(ユーザー数、機能モジュール数に応じて変動)
- 導入コンサルティング費用(年間1,000万円-1億円規模のプロジェクトも存在)
- カスタマイズ・開発費用(業務要件に応じた個別開発)
- データ移行費用(既存システムからのデータ移行作業)
- 教育研修費用(操作研修、管理者研修等)
月額費用には、システム利用料、保守サポート費用、クラウド型の場合はインフラ利用料が含まれます。オンプレミス型では、年間保守費用としてライセンス費用の15-20%程度が必要となります。
ROI(投資対効果)の算出方法と事例
OBIC7導入によるROIは、業務効率化による人件費削減、決算早期化による経営判断の迅速化、内部統制強化によるリスク軽減などの効果から算出されます。
一般的に、導入から2-3年で投資回収が可能とされており、特に人事業務の効率化や会計業務の自動化により、大幅な生産性向上が実現されています。
月次決算の早期化により、従来15日かかっていた作業が5日程度に短縮された事例や、経費精算の自動化により経理担当者の作業時間が50%削減された事例など、具体的な効果が多数報告されています。

OBIC7の導入実績と企業規模別活用事例
ERP累計導入社数シェアNo.1の実績詳細
OBIC7を提供する株式会社オービックは、国内ERPシステム市場において長年にわたってトップシェアを維持しています。累計導入社数は数千社を超え、特に日本企業の業務プロセスに最適化されたシステムとして高い評価を得ています。
上場企業での導入率も高く、東証プライム市場上場企業の約30%がオービック製品を利用しているという実績があります。この豊富な導入実績により、業界別のベストプラクティスが確立され、新規導入企業もスムーズな導入が可能となっています。
OBIC7の導入実績は、製造業、建設業、サービス業、卸売業など幅広い業界に及んでおり、業界特有の業務要件にも対応できる柔軟性が実証されています。
中小企業でのOBIC7活用事例
中小企業でのOBIC7活用では、限られた人員で効率的な業務運営を実現することが主な目的となります。特に会計業務の自動化により、経理担当者1名でも月次決算を迅速に完了できる環境が構築されています。
人事業務においても、勤怠管理から給与計算まで一連の業務が自動化され、人事担当者の負荷軽減と正確性向上が同時に実現されています。ワークフロー機能により、稟議や承認プロセスもペーパーレス化され、業務スピードが大幅に向上しています。
クラウド型の導入により、システム運用の専門知識を持たない中小企業でも安心して利用できる環境が提供されており、ITコストの削減にも貢献しています。
大企業・上場企業での導入成功事例
大企業での導入では、複数事業部や子会社を含む連結会計への対応が重要な課題となります。OBIC7の連結会計機能により、グループ企業全体の財務情報を統合管理し、迅速な連結決算が可能となっています。
内部統制の観点では、上場企業に求められる厳格な統制環境をシステム側で自動的に構築し、監査対応の効率化を実現しています。データの変更履歴や承認フローが自動記録されるため、監査証跡の整備も容易です。
大規模な組織では、部門間のデータ連携が複雑になりがちですが、OBIC7の統合データベースにより、リアルタイムでの情報共有が実現され、経営判断の迅速化に貢献しています。
業界別(製造業・サービス業・建設業等)の活用パターン
製造業では、OBIC7の生産管理機能を活用し、受注から出荷まで一貫した管理が行われています。原価計算機能により、製品別の詳細な原価把握が可能となり、収益性の向上に寄与しています。
建設業では、工事進行基準への対応機能を活用し、長期間にわたる工事プロジェクトの収益管理が適切に行われています。固定資産管理機能により、建設機械や設備の管理も効率化されています。
サービス業では、顧客管理機能と会計機能を連携させ、顧客別の収益性分析や、サービス提供コストの詳細把握が実現されています。経費精算機能により、営業活動に伴う経費管理も効率化されています。

OBIC7と他のERPシステムとの比較・評判
主要ERPシステム(SAP・Oracle・NetSuite等)との機能比較
OBIC7と海外製ERPシステムとの最大の違いは、日本の商慣習や法制度への対応度です。SAPやOracleなどの海外製システムは、グローバル標準の業務プロセスに最適化されており、日本独自の要件への対応にはカスタマイズが必要になることが多くあります。
一方、OBIC7は日本企業の業務プロセスを前提として設計されているため、導入時のカスタマイズ工数を大幅に削減できます。特に会計業務における法定帳票の対応や、人事業務における労働法制への対応は、OBIC7の大きな優位性となっています。
NetSuiteなどのクラウド型ERPと比較すると、OBIC7は日本企業特有の複雑な承認フローや、部門別管理会計への対応において優れた機能を提供しています。
OBIC7の良い評判・口コミの分析
OBIC7に対する評判として最も多く挙げられるのは、日本企業の業務に最適化された使いやすさです。特に会計業務においては、日本の会計基準や税制に完全対応しており、システム導入後すぐに実業務で活用できる点が高く評価されています。
サポート体制についても良好な評判が多く、株式会社オービックの手厚いサポートにより、システムトラブル時の迅速な対応や、法改正時のタイムリーなアップデートが提供されている点が評価されています。
導入実績の豊富さも安心材料として挙げられており、同業他社での導入事例を参考にできることや、業界特有の課題への対応ノウハウが蓄積されている点が評価されています。
改善を希望する評判・課題点の整理
OBIC7に対する改善要望として挙げられるのは、ユーザーインターフェースのモダン化です。長年の開発により機能は充実していますが、画面デザインや操作性において、より直感的な操作を求める声があります。
また、他システムとのデータ連携については、API機能の充実を求める要望があります。特に最新のクラウドサービスとの連携において、より柔軟な連携機能の提供が期待されています。
コスト面では、中小企業にとって初期導入費用の負担が大きいという意見もあり、より段階的な導入プランの充実が求められています。
他システムからOBIC7への移行メリット
既存の個別システムからOBIC7への移行により、データの一元管理が実現され、重複入力の削減や情報の整合性向上が図られます。特に複数のシステムを利用していた企業では、システム運用コストの削減効果も大きくなります。
海外製ERPからの移行では、日本の商慣習への適合度が大幅に向上し、カスタマイズコストの削減が期待できます。また、日本語でのサポート体制により、運用時の問合せ対応もスムーズになります。
レガシーシステムからの移行では、最新のセキュリティ機能や法制度対応により、コンプライアンス面でのリスク軽減が実現されます。クラウド型への移行により、システム運用の負荷軽減も同時に達成できます。

OBIC7導入時の注意点と検討すべきポイント
導入前に確認すべき自社の業務要件
OBIC7の導入を成功させるためには、自社の業務要件を詳細に整理し、ERPシステムに求める機能を明確化することが最重要です。企業活動の中で現在抱えている課題や改善したい業務プロセスを洗い出し、OBIC7が提供するソリューションとの整合性を慎重に検討する必要があります。
特に会計業務や人事業務においては、既存の業務フローとOBIC7の標準機能との差異を把握し、カスタマイズの必要性を事前に評価することが重要です。企業規模に応じて必要な機能や管理レベルが異なるため、自社の規模と成長計画を考慮した要件定義を行う必要があります。
また、他のシステムとのデータ連携要件や、既存のワークフロー機能との統合可能性についても詳細に検討しなければなりません。これらの要件が曖昧なまま導入を進めると、後々の運用において大きな課題となる可能性があります。
システム導入プロジェクトの進め方と期間
OBIC7の導入プロジェクトは、企業規模や導入範囲によって期間が大きく異なります。一般的には、小規模企業で3~6ヶ月、中規模企業で6~12ヶ月、大企業では1年以上の期間を要することが多いです。
プロジェクトの進行においては、段階的なアプローチを採用することが推奨されます。まず会計システムから導入を開始し、安定稼働を確認した後に人事業務や他の業務領域に展開していく方法が効果的です。
また、株式会社オービックの導入支援サービスを活用する場合、専門コンサルティングファームとの連携も検討する必要があります。コンサルティング費用は年間1000万円から1億円程度の相場となるため、プロジェクト予算に含めた計画立案が重要です。
操作教育・社内研修の重要性と計画立案
OBIC7導入における最大の成功要因の一つは、ユーザーの操作習熟度です。ERPシステムの機能を十分に活用するためには、体系的な教育プログラムの策定が不可欠です。
研修計画においては、役職や業務内容に応じたカリキュラムを設計し、段階的なスキルアップを図る必要があります。特に管理職層には、システムから得られる情報を経営判断に活用する方法について重点的に教育することが重要です。
また、システム稼働後も継続的な教育とサポート体制を整備し、新機能の活用や業務改善提案を促進する仕組みを構築することで、投資効果を最大化できます。
データ移行時の注意点とリスク対策
既存システムからOBIC7への移行において、データの正確性と整合性を保つことは極めて重要な課題です。特に会計データや人事データについては、移行エラーが企業活動に深刻な影響を与える可能性があります。
データ移行の注意点として、まず移行対象データの範囲と期間を明確に定義し、データクレンジングを十分に実施する必要があります。また、移行テストを複数回実施し、データの整合性を段階的に検証することが重要です。
リスク対策としては、移行作業のロールバック計画を事前に策定し、問題が発生した場合の対応手順を明確化しておくことが不可欠です。さらに、移行作業中は業務への影響を最小限に抑えるため、適切なタイミングでの実施とバックアップ体制の整備が求められます。

OBIC7が適している企業の特徴と導入判断基準
OBIC7導入に最適な企業規模・業種の特徴
OBIC7は、中堅・中小企業から大企業まで幅広い企業規模に対応できるERPシステムとして設計されています。特に売上高50億円から500億円規模の企業において、その機能と価格のバランスが最も効果的に発揮される傾向があります。
業種的には、製造業、建設業、卸売業、サービス業など、複雑な業務プロセスを持つ企業でのメリットが大きいとされています。これらの業界では、OBIC7の豊富な機能と業界特化型のソリューションが企業活動の効率化に大きく貢献します。
また、グループ企業を持つ組織や、将来的な事業拡大を計画している企業にとって、OBIC7の拡張性とデータを一元管理する機能は特に価値が高いといえます。
既存システムとの連携可能性の検討
OBIC7の導入検討において、既存システムとの連携可能性は重要な判断基準となります。特に長年使用してきた個別システムがある場合、段階的な移行計画を策定する必要があります。
OBIC7は他のシステムとのデータ連携に対応する豊富なインターフェース機能を提供しており、既存の基幹システムとの共存も可能です。ただし、連携の複雑さやメンテナンス性を考慮し、長期的な視点でのシステム統合計画を立案することが重要です。
導入効果を最大化するための事前準備
OBIC7の導入効果を最大化するためには、業務標準化と組織体制の整備を事前に実施することが成功の鍵となります。システム導入前に業務プロセスの見直しを行い、効率的なワークフローを設計することで、OBIC7の機能を最大限に活用できます。
また、システム管理者の育成と、各部門のキーユーザーの選定・教育も重要な準備項目です。これらの人材が中心となって、組織全体のシステム活用を推進する体制を構築する必要があります。
導入成功のための社内体制づくり
OBIC7導入を成功に導くためには、経営層のコミットメントと適切なプロジェクト体制の構築が不可欠です。プロジェクトリーダーには、業務知識とシステム知識の両方を持つ人材を配置し、各部門からの協力を得られる体制を整備することが重要です。
また、変更管理の観点から、従業員への十分な説明と理解促進を図り、システム導入に対する組織的な合意形成を行うことが、スムーズな導入と効果的な活用につながります。

OBIC7に関するよくある質問(FAQ)
OBIC7はどのような企業規模に適していますか
OBIC7は中小企業から大企業まで幅広い企業規模に対応しています。特に従業員数50名以上、売上高10億円以上の企業において、ERPシステムとしての機能を十分に活用できます。企業規模に応じたカスタマイズが可能で、成長に合わせてシステムを拡張することができます。
クラウド型とオンプレミス型のどちらを選ぶべきですか
選択は企業のIT戦略と要件によって決まります。クラウド型は初期コストが抑えられ、保守管理の負担が軽減される一方、オンプレミス型は高いカスタマイズ性と完全な管理権限を持てます。セキュリティ要件、既存システムとの連携、長期的なコスト計画を総合的に検討して選択することが重要です。
導入期間はどの程度かかりますか
企業規模と導入範囲によって異なりますが、一般的には3ヶ月から1年程度の期間を要します。段階的導入を行う場合は、第一段階として会計業務から開始し、順次人事業務や他の機能を追加していく方法が効果的です。
既存データの移行は可能ですか
はい、既存システムからのデータ移行は可能です。OBIC7は多様なデータ形式に対応しており、CSV形式やExcel形式でのデータインポート機能を提供しています。ただし、データの品質確保と整合性チェックのため、十分な移行テストを実施することが重要です。
システムの操作は難しいですか
OBIC7は直感的な操作画面を採用しており、一般的なオフィスソフトに慣れた方であれば比較的習得しやすい設計となっています。また、株式会社オービックでは充実した研修プログラムとサポート体制を提供しており、スムーズな操作習得をサポートします。
サポート体制はどのようになっていますか
株式会社オービックでは、電話サポート、リモートサポート、オンサイトサポートなど多様なサポートサービスを提供しています。また、定期的なバージョンアップやセキュリティ更新も含まれており、安心してシステムを運用できる体制が整備されています。

